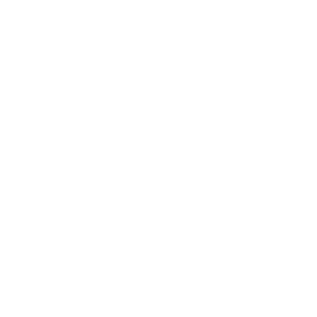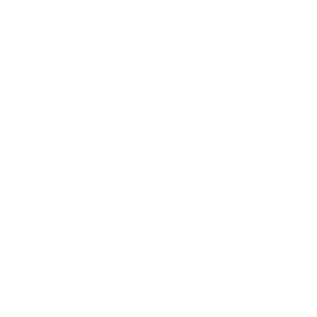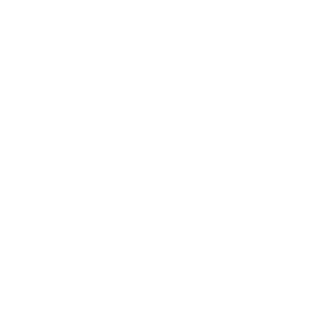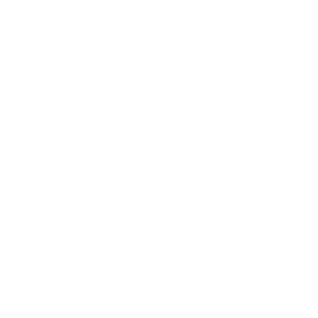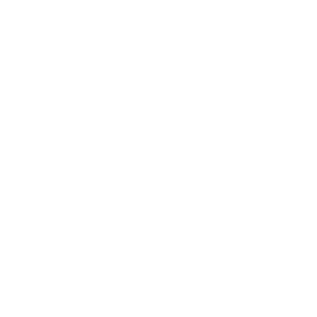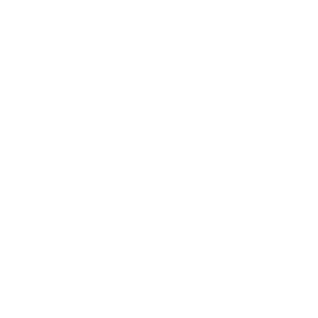これから始まる金融教育
掲載:2022月7月4日2022年4月
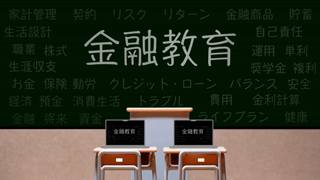
今年2022年4月より新しい学習指導要領がスタートし、高校の家庭科の授業で金融教育が行われるようになりました。
メディア等でも取り上げられていたので、ニュースで見た方も多いかと思います。
また、同じように2022年4月より成人年齢の引下げも行われました。それにより、18歳からクレジットカードを作ることができるようになったり、ローンを親権者の同意なく組めるようにもなりました。
そういった情勢を踏まえて、高校生から金融教育が始まることとなりました。
金融教育とはなにか

金融と聞くと仰々しく聞こえ、株でお金を増やすような取引など難しそうなイメージがありますが、そうではありません。
簡単に言ってしまうと一人一人が経済的に自立し、社会の一員として生活できるようにするための必要な知識です。
高校を卒業し、そこから人生は60年以上続きます。高校生までは自分が使うお金だけを考えて生活できていましたが、進学・就職をすることでお金の使い方が生活に直接的にかかわってくるようになります。
また、収入や支出だけでなく、貯蓄やローン、社会保障・保険制度、金融トラブルについても幅広く学びます。
生活をしていくうえでお金そのものだけでなく、人生設計までを考えていく内容となっています。
なぜ、金融教育をするのか
社会情勢が変わりいくなか、金融教育を進めていく理由として、ここ最近で大きく動いたことがいくつを紹介します。
老後資金2,000万円問題
2020年の終わりごろに大きくニュースとなった「2,000万円問題」を覚えていますか?
金融庁のワーキンググループが試算した結果、老後に必要な資金が2,000万円不足しているという報告をだし、物議をかもしました。
そういったことを背景に、いかに早く資産形成を行い、計画的に老後資金を作ることの必要性を教えていく必要があります。
日本の金融教育の遅れ
日本では、子供にお金の話をしないといった考え方であったり、「金融教育とはなにか」で書いた通り、金融というだけで難しそう、株などハイリスクなことを覚えさせたくないなどの、ネガティブなイメージが先行しており、そういったことを重点的に教えることをしていませんでした。
しかし、諸外国においては、ゲームなどを利用した勉強(アメリカ)であったり、3歳ごろから絵本などを使い、段階的に教育する(イギリス)など子供たちが興味を持ち、遊びの中から勉強もできるようになっており、お金について考えることが当たり前の教育をしています。
成人年齢の引下げ
冒頭にも書きましたが、金融教育の開始と同じくして、成人年齢が20歳から18歳に引下げられました。
それに伴い、契約行為を単独で出来るようにはなりましたが、社会経験のない状態でローンなどを使えるようになってしまうことから、金融リテラシーの向上が必要となりました。
子供たちと金融のこれから
金融教育を通じて、人生の先に向けて確実にお金を増やす方法や、いざという時にお金が無くならないようにするためにも、早い教育が必要になってきます。
金融業界もキャッシュレスやフィンテックなど新しい技術ができ、情勢もどんどん変化しています。
そういったなかで、将来困らないためにも子供だけでなく、大人の私たちも勉強していく必要があると感じました。
参考:金融庁「高校向け 金融経済教育指導教材の公表について」次回更新予定
次回の掲載予定は2022年8月8日です。
実は奥が深い自動車ローン:番外編
コラムに関するご意見・リクエストは
-
- メールフォームにて
24時間365日受付中
- メールフォーム
- メールフォームにて